
夫婦杉、と呼ばれる2本杉や楠などが並んでいる神社は全国的に珍しくないが、そういうものとは異なり、一つの神社の敷地内に他人のような距離感で大きさを競うようにそびえる巨木を有した神社がある。今回はそんな神社を4つ紹介していきたい。
離れて立つ2本の巨木神社4選
八柱神社 (長野県根羽村)
長野県の最南端に根羽村という地がある。星空で有名な阿智村のさらに南西に進んだ先にあるのだが、この村に八柱神社は鎮座する。

長野県神社庁によれば、創建は不詳で明治40年当時の長野県知事大山綱昌が小社無格社を合併するという訓令を出したことで、村社2社、無格社7社を遷座し41年に合祀したという。

石段を登り、まず飛び込んでくるのが境内ど真ん中にそびえる巨杉である。

この杉をみようと社殿に向かう石段をのぼると、


なんと社殿の向かって左手にほぼ同じ体格の巨杉が鎮座する。


この2本を併せて「八柱の神代杉」と呼び長きにわたって大切にされてきた。いずれも幹回り7m超えの巨木である。
この神社は長野県内第一の巨木「月瀬の大スギ」に向かう途中にある(関東から中央道などで向かった場合)。
巌鬼山神社 (青森県弘前市)

青森県の誇る「津軽富士」こと岩木山 その南東部の麓には津軽国一宮である岩木山神社が鎮座する。


参道の背後に岩木山を望む壮麗な神社である。
そんな岩木山神社から北、岩木山から見ると北東部「鬼門」に鎮座するのが巌鬼山神社 (がんきさんじんじゃ)である。

ひと気のない林道のような道もあり不安の中進むと道が開けて鳥居があらわれる。


一宮であり常に多くの参拝者が絶えない岩木山神社とは対照的に森に囲まれ静謐な空気が流れる。


拝殿の手前に巨大な杉の木がたつ。
そして拝殿の向かって左手にこれまた巨杉がドンとたつ。


決して離れているわけではないが並んでいるとも言えないこの2本、計算して配置されたものでない魅力がある。


七崎神社 (青森県八戸市)
再び青森県、七崎神社とは八戸市西部に鎮座する神社である。七崎神社はかつて「七崎観音」と称された観音堂を起源とする。明治維新の神仏分離に際し観音堂の本尊は移され元の観音堂が七崎神社と改められた。


境内に入るとすぐに巨杉が聳え立つ。834年七崎山に遷宮した際に植えた9本の(7本ともいわれる)うち3本が現在も残っている。


参道を進み右手を向くともう一本の巨木がドシっと立つ。

斜面にあるとインパクトもなかなか大きい。


拝殿のすぐ近くに3本目が立つ。こちらも充分大きいがさすがに前の2本には及んでいない
吉田八幡神社 (茨城県常陸大宮市)
茨城県常陸大宮市の、国道293号を栃木県方面へ進んでいくと小田野川沿いに三浦杉公園がある。


季節によってヒマワリ、アヤメなど美しい花を楽しむことができるこの公園ののどかな風景のなか、奥に見える鳥居をくぐると急に深い森と化す。

石段を登っていくと奥のほうに明らかに縮尺のおかしい2本の巨樹がそびえ立つのが見える。

期待を胸に登っていく…

…がここから先は進めないようだ。かつて落枝があったためらしい。

樹齢約800年、幹回り8m超えの巨体が2本続けてたつ様は迫力満点である。かつては鎌倉杉と呼ばれていたそうだが、久寿2年(1155年)相模国三浦大介義明が下野国那須野々原に九尾の狐退治に行く途中にここに参拝し植えた杉である、という話を聞いた徳川光圀公により「三浦杉」と命名されたという。
参考・出典
・長野県神社庁HP
・各神社境内案内板
・『国文学年次別論文集国文学一般 昭和58(1983)年』 朋文出版 出版 学術文献刊行会 編 1984年
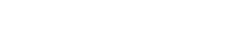



コメント