〒888-0221 宮崎県串間市大納

概要
宮崎県南部、串間市の海沿いを走る国道448号から細い砂利道を約1.5km進んだ先にある神社。
創建は鎌倉時代と伝えられているが、天保8年(1837年)の大洪水で社殿とともに宝物・記録類・創建や改修の記録まですべて流され、詳細は不明となっている。かつては「飛龍三社大権現」と呼ばれ、鵜戸神宮・榎原神社と並び、時の将軍から早天祈願 (朝早くに行う祈願、あるいは朝に集まって祈る儀式)などの祈願所として指定される。古来より岬を通る船の海上安全や大漁祈願、農業の豊作祈願のために、日南油津の貿易商や南郷目井津の漁師たちが多く参拝したという。明治維新後の廃仏毀釈と神社統合により、明治6年5月に都井神社へ合祀されるも、地元氏子の強い願いにより明治15年9月に復社が許され社殿が改築、「名谷神社」と改称される。
参道の砂利道は離合も容易ではなくアクセスするには決して楽な道ではない。ただその先の境内、社殿の奥には立派な滝が流れる神秘的な空間が広がっている。訪れたものだけが味わえる静謐なひとときである。
おすすめ度:★★★★☆
秘境度:★★★★★
御祭神
水速女命 (みずはやめのみこと)、誉田別命 (ほんだわけのみこと)、少彦名命 (すくなひこなのみこと)
レポート














例祭
10月18日 例祭 2月18日 新年祭
アクセス
車:JR串間駅より約35分
徒歩:JR串間駅よりよかバス名谷黒井線 名谷下車徒歩約35分
駐車場
あり
参考・出典
・境内由緒書
・『宮崎県神社誌』宮崎県神社庁 出版・編 1988年
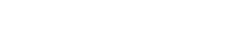



コメント